近年、日本の軽トラック(軽トラ)が海外で高い人気を集めています。
小型ながら頑丈、多用途に使用可能、カスタマイズ性、農業、配送、建設現場などでの移動と、さまざまな分野で重宝され、東南アジアやアフリカ、北米などの国々から多くの引き合いがあります。
特に日本での中古軽トラックは品質が高く、コストパフォーマンスにも優れていることから、中古車輸出ビジネスの中でも注目のジャンルとなっています。
本記事では、軽トラがなぜ海外で人気なのか、主な輸出先や市場の動向、輸出を始めるために必要な準備と手続き、さらには仕入れ時のポイントや輸出時のリスク・メリットまで、初心者にもわかりやすく解説します。
これから軽トラの海外輸出ビジネスを始めたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
それでは早速行きましょう!
軽トラック(軽トラ)が海外で人気の理由

先ほどお伝えした通り、日本の軽トラック(通称:軽トラ)が世界各国で注目を集めております。
とくに中古車市場では、軽トラが「小さくてもパワフル」「用途が広くて経済的」といった理由から、多くのバイヤーの関心を引いており、その需要は年々増加傾向にあります。
ここでは、なぜ軽トラが海外でこれほどまでに評価されているのか、その主な理由を詳しく解説します。
小回りが利き、狭い道でもラクラク走行
軽トラの大きな特徴のひとつが、そのコンパクトなサイズ感です。
全長約3.4m、全幅約1.48m以内というボディサイズは、都市部の狭い路地や未舗装の山道、農道などでも取り回しがしやすく、海外の農村地域や建設現場、山間部などにおいて非常に重宝されます。
たとえば、東南アジア諸国では道路インフラが十分に整備されていない地域が多く、軽トラのような小回りの利く車両が特に重宝されるのです。
加えて、米国のように広大な敷地を持つ農場でも、大型トラックとは別に「作業車」として活躍しています。
高い燃費性能と維持費の安さでコスパ抜群
日本の軽トラは、660ccの小排気量エンジンを搭載しており、1リットルあたり約17〜20km程度の燃費性能を持っています。
これは海外の一般的なピックアップトラック(平均10〜12km/L程度)と比較しても圧倒的に低燃費です。
燃料費が家計やビジネスに与える影響が大きい国々では、維持費の安さは購入時の大きな決め手になります。
また、税金や保険料といった維持コストも軽トラなら低く抑えられるため、長期的に見てもコストパフォーマンスが高い乗り物として評価されています。
日本製ならではの高品質と耐久性
日本国内では定期点検や車検制度が厳格に運用されており、多くの軽トラがしっかりとメンテナンスされた状態で中古市場に出回ります。
さらに、日本人特有の「ものを大切に使う文化」もあり、10年以上使用された車両でも良好な状態が保たれているケースが少なくありません。
そのため、海外では「日本の中古車は品質が良い」「壊れにくい」「安心して使える・買える」といった信頼が定着しており、軽トラにもそのイメージが強く反映されていると言えます。
法規制の緩和や為替の影響も追い風に
米国では「25年ルール」と呼ばれる規制緩和の制度があり、製造から25年以上経過した車両は安全基準や排ガス規制をクリアせずとも輸入が可能になります。
この制度により、1990年代〜2000年代初頭の軽トラが多くアメリカ市場に流通しはじめおり、一定のニーズが形成されました。
さらに、近年の円安ドル高傾向は、日本からの輸出価格を割安に感じさせる要因となっており、軽トラの仕入れ・転売ビジネスにとっても絶好のタイミングといえます。
軽トラック(軽トラ)の主な輸出先とその特徴

日本国内では農業や建設業、配送など多彩な用途で活躍している軽トラック(軽トラ)。
その機能性と耐久性の高さは海外でも評価され、近年では世界各国で輸出台数が増加しています。
ここでは、2025年時点で特に注目されている主な輸出先を5か国ピックアップし、それぞれの地域でのニーズや特徴を詳しくご紹介します。
アラブ首長国連邦(UAE)|中古車輸出のハブ市場として存在感
UAEは日本の中古車輸出市場において、最大級のシェアを誇る重要な国のひとつです。
特にドバイは世界中の中古車が集まる「再輸出のハブ」としても知られており、日本の軽トラもこのルートを通じて中東やアフリカ諸国へと再販されています。
現地では建設現場での資材運搬、農地での作業、都市部の配送用など幅広い用途で活用されています。
高温乾燥地帯でも耐えうる日本車の耐久性と、狭い路地でも小回りの利く利便性が評価されており、今後も安定した輸出先として期待されています。
ロシア|寒冷地での強さと再販ネットワークの強固さ
ロシアはかつて日本の中古車輸出先として非常に大きな市場でした。
近年は経済制裁や輸入規制により取引は制限されていますが、それでもウラジオストクなど極東地域では日本の軽トラの人気は根強く、シベリアや内陸部へも流通しています。
軽トラは積雪や氷点下の環境下でもエンジンの始動性が高く、過酷な道路事情にも耐える構造となっているため、寒冷地での農作業や林業、物資輸送などに活用されます。
また、ロシア国内だけでなく、旧ソ連諸国へと横展開されるケースも多く、ネットワークの広さが強みとなっています。
モンゴル|オフロード性能と低コスト輸送が評価
モンゴルでは国土の大半が草原地帯で、未舗装の道路や山岳地帯での走行が日常です。こうした環境では、軽量で車高があり、頑丈なサスペンションを備えた軽トラの性能が大いに発揮されます。
現地では家畜の輸送、建築資材の運搬、小規模商店での商品配送などに使われており、その用途は非常に多岐に渡ります。
また、モンゴルは日本からの距離が比較的近いため、輸送コストが抑えられることも輸出先としての魅力のひとつです。
タンザニア|アフリカ市場で拡大する日本車需要
アフリカ諸国の中でも、タンザニアは特に日本からの中古車輸入が盛んな国です。
軽トラは現地での農作物の運搬や市場への出荷、小規模工事の資材輸送などに使われており、生活やビジネスのインフラを支える“働くクルマ”として存在感を高めています。
また、タンザニアはケニアやウガンダなど周辺国への中古車の流通拠点ともなっており、日本から到着した軽トラが港湾都市ダルエスサラームを経由して周辺国へ再販されることも少なくありません。
軽トラの経済性とメンテナンスのしやすさが、こうしたローカルニーズと見事に合致しています。
アメリカ|農園やDIY用途での活躍
アメリカは自然豊かな国土を活かし、畜産業や野菜農業経営が盛んな国です。軽トラはそのコンパクトさと扱いやすさが農作業に適しており、小型のトレーラーを牽引して使う事例も多く見られます。
また、アメリカでは「自分で直して使う」という文化が根付いており、DIY愛好家の間でも軽トラは人気です。パーツの供給や修理のしやすさも評価されており、個人購入層を中心に需要が拡大しています。
なお、25年ルール適用車両に限り輸入可能です。上記でお伝えした農業や畜産用途はもちろんの事、コレクター界隈で密かなブームになっています。
そのほかの注目国
ニュージーランド:畜産業や果樹園経営が盛んな国で、軽トラに小型トレーラーを牽引して使用する等で、個人購入層を中心に需要が拡大。
ケニア:東アフリカ最大の中古車輸入国。タクシーや運搬業務で軽トラが活躍。
フィリピン・タイ・インドネシア:日系企業の多い東南アジアでは、軽トラの扱いやすさが支持され、商用需要が拡大中。
これらの国々では、軽トラのコンパクトながら多機能という特性が、現地の社会インフラやビジネスにぴったりとマッチしており、「日本の軽トラ=信頼できる商用車」として高く評価されています。
軽トラック(軽トラ)の市場動向と今後の展望

軽トラックは、農業用や配送用といった商業車両としてだけでなく、近年はレジャーや趣味用途でも注目を集めており、国内外でその需要は多様化しています。
とくに2020年代に入ってからは、海外市場での中古軽トラの需要が急増しており、輸出台数の推移や国際的な評価からも「世界で通用する働くクルマ」としての地位を確立しつつあります。
以下では、グローバルな需要動向とともに、今後の成長可能性、注目される技術革新や市場の変化について詳しく解説します。
世界市場の成長性:年々高まる軽トラの存在感
軽トラックは、日本国内では「軽自動車」というカテゴリーに分類されるものの、海外では「ミニトラック」「マイクロトラック」などとして独自の市場を形成しています。
特に近年は、都市部での小回りの良さや維持費の安さが評価され、農村部のみならず都市部のビジネスにも浸透しはじめています。
世界のミニトラック市場規模は、2023年時点で約181億ドル(約2.7兆円)に達し、今後は2025〜2033年にかけて年平均成長率(CAGR)4.5〜5.8%の伸びが見込まれています。
需要が伸びているのは東南アジアやアフリカだけでなく、アメリカ、オセアニア、中東諸国など世界中に広がりを見せています。
米国市場の急拡大と“25年ルール”の影響
特に注目されているのがアメリカ市場です。
アメリカでは「25年ルール(25-Year Import Rule)」という制度により、製造から25年を経過した日本車であれば、安全基準や排出ガス規制の対象外として比較的スムーズに輸入が可能になります。
この制度を活用し、1990年代〜2000年代初頭の軽トラ(スズキ キャリイ、ダイハツ ハイゼット、ホンダ アクティなど)を輸入する動きが活発化。特にオフロード、キャンプ、狩猟、農園作業などの用途において、「必要最低限で扱いやすい小型車」として高い評価を受けています。
2023年には約7,000台超の日本製軽トラがアメリカに輸出されており、これは10年前(約700台)の約10倍という驚異的な伸びです。
特に、過去10年で米国への中古軽トラ輸出台数は10倍に増加(784台→7050台)し、経済性や利便性が注目される一方、規制や競合との競争が課題となっている。
引用元:Merkmal(メルクマール):スズキ、軽トラで「CES」に挑戦! 中古輸出10年で10倍の追い風、米国市場席巻なるか?
今後もこの成長は継続する見込みであり、日本国内での仕入れ→輸出→再販というビジネスモデルも成熟しつつあります。
アジア・アフリカにおける社会インフラとしての軽トラ
アジアやアフリカの新興国では、道路インフラや経済状況の影響から、大型トラックよりも低価格・低維持費で導入できる軽トラの存在が重宝されています。特に農村部では、軽トラが唯一の交通手段や商業車両となるケースも珍しくなく、地域の経済活動を支えるインフラの一部といっても過言ではありません。
また、港湾都市を起点とした「ハブ国」への輸出も拡大しており、たとえばUAE(アラブ首長国連邦)では日本の軽トラが再販され、周辺のアフリカ諸国へ流通するという動きが加速しています。
為替・物流コスト・国際関係の影響
2022年以降、円安傾向が続いたことにより、日本からの輸出は相対的に「割安感」が強まり、海外のバイヤーにとって非常に買いやすい環境が整いました。
また、コンテナ運賃や海上輸送費も2025年にかけて若干の落ち着きを見せており、これも輸出台数増加の追い風となっています。
一方で、ロシア向けの輸出については、ウクライナ情勢に起因する経済制裁の影響で不透明な状況が続いており、マーケットの分散が必要とされています。
こうした地政学的リスクを回避するため、今後はアフリカ、東南アジア、南米といった地域への戦略的な展開が求められるでしょう。
今後の注目点:電動化・規制対応・市場の細分化
軽トラの将来的な輸出において、注目すべきは次の3つのテーマです。
- 電動軽トラの台頭
環境規制の強化に伴い、EV(電気自動車)仕様の軽トラの開発が各メーカーで進められています。すでに一部の自治体や企業では「EV軽トラ」を業務用車両として導入しており、輸出市場においても今後一定の需要が期待されます。
- 法規制の変化に対応できる柔軟性
各国での車両輸入に関する規制は年々厳しくなっている傾向があります。たとえば右ハンドル車の制限や、安全基準・排ガス規制など、国によって異なる要件への柔軟な対応が求められています。今後はより細分化された「輸出仕様軽トラ」も登場する可能性があります。
- 趣味・パーソナル用途での市場拡大
従来は業務用としてのイメージが強かった軽トラですが、近年ではカスタムベースやレジャー用途での利用が増加。特にアメリカでは「ミニトラック文化」として愛好者が増えており、中古市場にも影響を与えています。
軽トラは、単なる「農作業用の小型車」という枠を超え、いまやグローバルで多様な用途に対応できる“プロフェッショナルユースの軽商用車”として進化を遂げています。
輸出市場の安定的な成長、為替や輸送環境の改善、そしてEV化や市場の細分化といった変化にどう適応するかが、今後のビジネスチャンスを大きく左右するでしょう。
軽トラック(軽トラ)の海外輸出を始めるために必要な準備と手続き

軽トラックを海外へ輸出するには、仕入れから書類作成、通関・輸送の手配まで、段階的に必要な手続きがあります。
初めて輸出に取り組む方にとっては煩雑に感じるかもしれませんが、流れを理解しておけばスムーズに進められます。
この章では、実務として押さえておくべき6つの準備・手続きについて、順を追って詳しく解説します。
古物商許可の取得
まず、軽トラックを仕入れて再販する場合は、古物商許可が必要です。これは中古車や中古パーツを売買する際に法律で定められているもので、営業活動として継続的に軽トラを扱うなら必須となります。
古物商許可は、営業拠点を管轄する警察署の生活安全課で申請します。申請には住民票、身分証明書、誓約書、略歴書、営業所の賃貸契約書などが必要で、申請から取得まで1〜2ヶ月ほどかかるのが一般的です。
この許可がないまま取引を繰り返すと、古物営業法違反で罰則を受ける可能性があるため、事業として輸出を行う場合には最初に取得しておきましょう。
輸出抹消仮登録証明書または輸出予定届出証明書の取得
軽トラを海外へ輸出する際は、日本国内での登録を抹消し、輸出用の証明書を取得する必要があります。これに該当するのが以下の2種類の証明書です。
輸出抹消仮登録証明書:通常、まだ一時抹消されていない車両に使用。
輸出予定届出証明書:すでに一時抹消済の車両に対して使用。
いずれも運輸支局(普通車)または軽自動車検査協会(軽自動車)で発行され、税関での申告や輸出通関時に必須の書類となります。
手続きには、車検証、ナンバープレート、印鑑証明書、所有者の実印、申請書類などが必要です。証明書の有効期限は6ヶ月間で、輸出前の早めの取得が推奨されます。
必要書類の準備
軽トラックを輸出する際には、通関・輸送・現地登録のために複数の書類を整備する必要があります。主なものは以下のとおりです。
インボイス(Invoice):取引の明細書。車両の価格、仕様、数量、取引条件(FOB/CIFなど)を記載。
パッキングリスト(Packing List):輸出する車両の重量・寸法・台数を明記。
船荷証券(B/L):フォワーダー(貨物業者)や海運会社が発行する、貨物の受領と運送契約の証明。
輸出抹消登録証明書:前述の通り。車両が正式に日本の登録を抹消された証明。
船積前検査証明書(必要に応じて):国によっては、現地の輸入規制により、輸出前検査(JEVIC、EAAなど)が必要な場合があります。
これらの書類が不備なく整っていないと、税関手続きが滞ったり、現地での登録ができなかったりするため、慎重に準備を進めましょう。
輸送手配と通関手続き
車両を海外へ届けるための輸送と通関業務は、輸出ビジネスの重要なステップです。
■ フォワーダーや海貨業者の選定
輸出の経験が浅い場合は、通関業務や輸送を専門に代行してくれるフォワーダー(貨物取扱業者)と契約するのが安心です。業者によっては、インボイス作成や輸出申告、コンテナへの積載手配まで一括で対応してくれる場合もあります。
■ 船便手配(コンテナorRoRo)
輸送方法としては、コンテナ便とRoRo(Roll on/Roll off)船があります。RoRoは車両をそのまま船に積み込む方式で、大量輸送に向いています。一方、コンテナは少量でも対応できる柔軟性があります。
■ 通関申告
通関時には、前述の書類を元に税関へ輸出申告を行います。場合によっては検査が実施されることもありますが、問題がなければ輸出許可書が発行され、正式に出荷が可能となります。
車両の洗浄と検疫対策
輸出先によっては、車両に付着した泥や植物の種子などが「有害生物の侵入リスク」と見なされ、検疫で拒否される場合があります。特に農業が盛んな国(オーストラリア、ニュージーランドなど)では、検疫基準が非常に厳しいです。
そのため、車両の外装・下回り・タイヤ・荷台・室内などの徹底洗浄が必須とされるケースもあります。専用の車両洗浄業者による処理を依頼しておくと、トラブルを未然に防ぐことができます。
リサイクル料金の還付手続き
日本では車両購入時にリサイクル料金を支払う制度がありますが、軽トラを輸出した場合、この料金を還付してもらうことが可能です。
還付を受けるには、輸出後にリサイクル券、輸出抹消証明書、船荷証券、輸出許可書などを揃え、還付申請書を提出します。
手続きは郵送またはオンラインで行うことができ、申請から2〜3ヶ月程度で返金されるのが一般的です。
また、自賠責保険や自動車税についても、残存期間に応じて還付が可能です。こうした費用をしっかり回収することで、輸出ビジネスの収益性も高まります。
軽トラック(軽トラ)仕入れ時のポイント

軽トラを海外へ輸出するにあたり、仕入れの段階でどれだけ精度の高い選定ができるかが、最終的な収益や輸出の成否を左右します。
安く仕入れることだけが重要なのではなく、輸出先のニーズや規制に適した車両かどうか、車両の状態は輸送に耐えられるか、必要書類が揃っているかなど、複合的な観点から判断する必要があります。
この章では、輸出を前提とした軽トラックの仕入れ時に押さえるべきポイントを、5つの視点から解説します。
市場調査:輸出先国の需要と動向を把握する
まず最初に行うべきは、仕入れ対象車両が本当に売れるのかを見極めるための市場調査です。
国や地域によって軽トラに求められる条件は大きく異なります。
たとえば、アフリカ諸国では、耐久性・積載力重視、MT(マニュアル車)の需要が高い。
アメリカでは、25年ルールに適合した旧年式で、カスタムしやすい車両が人気。
モンゴルなど寒冷地では、4WDの軽トラが好まれ、エンジン始動性や錆びにくさが重視される。
市場の傾向を知らずに仕入れてしまうと、「輸出しても売れない」「現地の規制に合わず通関できない」などのリスクが発生します。
Google Trendsや貿易統計、輸出業者のレポート、SNSのコミュニティ情報など、複数の情報源から現地ニーズを把握するのが基本です。
信頼性のある仕入れルートを確保する
中古車の仕入れ方法にはいくつかありますが、輸出用の軽トラを仕入れる場合は、信頼できるルートを確保することが成功への第一歩です。
■オークションからの仕入れ
全国にある業者専用オークション(USS、TAA、JUなど)では、毎週数万台の中古車が取引されており、軽トラも多数出品されています。出品票には外装・内装の状態、修復歴、走行距離などが記載されているため、精査してから入札が可能です。
ただし初めての場合は、代行業者や仕入れパートナーを通じた参入が安心です。
■中古車販売店・輸出業者からの購入
車両の整備履歴が確認できる個体が多く、保証やアフターサポートがある場合もあります。また、輸出実績のある業者であれば、どの車両がどの国に向いているかをアドバイスしてくれるため、初心者にも心強い選択肢です。
■車両の状態を徹底的にチェックする
車両の外観やスペックが良く見えても、内部に大きな欠陥がある場合は輸送時のトラブルや現地でのクレームにつながりかねません。
以下の項目は、仕入れ時に特に注視したいポイントです。
走行距離:5万km未満は海外でも高評価。10万km以上でも整備記録があれば好印象。
エンジンの調子:アイドリング、始動性、異音、オイル漏れの有無などを確認。
トランスミッションの状態:スムーズにギアが入るか、クラッチの滑りはないか。
シャーシ・床下のサビや腐食:特に雪国で使われていた車両は要注意。構造部分に穴やヒビがあればNG。
改造・カスタムの有無:オリジナル状態を重視する国もあるため、過度な改造車は売れ残るリスクあり。
こうした点を確認し、できれば点検記録簿(整備履歴)や車検証のコピーも取得しておくと、輸出後のトラブル防止にもつながります。
輸出先国の規制・条件に合っているか確認する

各国では、輸入できる車両にさまざまな規制が設けられています。その代表例が以下です。
年式制限:南アフリカやナイジェリアなどでは、輸入できる車の製造年に制限がある。
排ガス規制:インドネシアやフィリピンでは、EURO規制や現地の排出ガス基準を満たす必要がある。
右ハンドル・左ハンドル規制:国や州によっては右ハンドル車の公道使用に制限がある。
25年ルール:アメリカでは製造から25年以上経過していない車両は基本的に輸入できない。
これらを無視して仕入れてしまうと、現地で通関できず輸出が無駄になるおそれがあるため、輸出予定先の輸入条件をあらかじめ調査しておくことが不可欠です。
仕入れ価格だけでなく、トータルコストで考える
仕入れ時に多くの人が見落としがちなのが、「安く買えても、最終的に利益が出るとは限らない」という点です。車両価格のほかにも、以下のようなコストが発生します。
- 国内輸送費(仕入れ先から港までの陸送費)
- 通関手数料・書類作成費
- 車両洗浄・消毒費(検疫対応)
- 海上輸送費(コンテナまたはRoRo船)
- リサイクル料金還付の有無
- 自賠責や自動車税の残額精算
これらをすべて含めた総コストをあらかじめシミュレーションし、期待される販売価格と照らし合わせて「どれくらいの粗利が取れるのか」を明確にしておくことが、安定した輸出ビジネスには欠かせません。
輸出手続きと物流の流れ
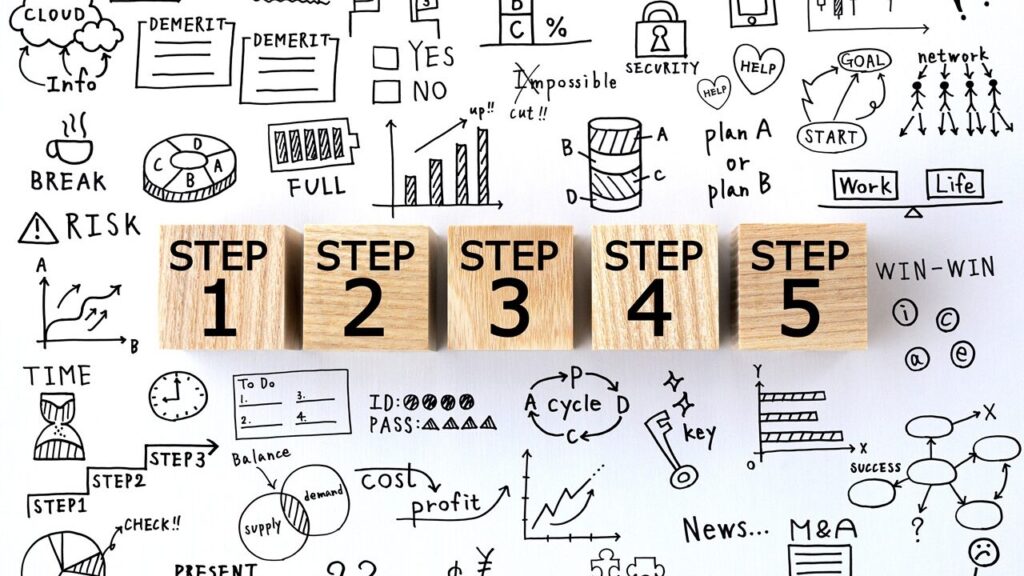
軽トラの輸出には、書類準備から通関・輸送・現地登録まで複数の工程があります。以下にその流れを簡潔にまとめます。
① 商談と契約
インボイス(請求書)や貿易条件(FOB/CIFなど)を取り決め、バイヤーと契約を結びます。
② 書類作成とフォワーダー依頼
インボイス・パッキングリスト・船積み指示書(S/I)を作成し、輸送や通関を担うフォワーダーを手配します。
③ 陸送と保税倉庫への搬入
車両を港の保税エリア(CYまたはCFS)に搬入します。ここで積み込み前の準備を行います。
④ 輸出通関と許可取得
必要書類を税関に提出し、通関検査を経て「輸出許可書」が発行されます。AEO認定業者を活用するとスムーズです。
⑤ 船積み(コンテナまたはRoRo)
コンテナ便:複数台をまとめて安全に輸送。
RoRo船:車を自走で搭載。大量輸送に向いています。
船荷証券(B/L)が発行され、輸出の証拠になります。
⑥ 海上保険加入(任意)
条件により、損害補償のための海上保険(CIF契約等)が必要です。
⑦ 書類送付と現地準備
B/Lや輸出許可書のコピーをバイヤーに送付し、現地通関・登録の準備を依頼します。
⑧ 輸入国での通関・登録
現地税関での検査、税金納付を経て正式に車両が登録されます。
⑨ リサイクル料金の還付申請(日本側)
輸出後、JARCに輸出抹消証明書やB/Lを提出することで、支払済みのリサイクル料金の返金が受けられます。
軽トラック(軽トラ)の海外輸出時のメリット

軽トラック(軽トラ)の海外輸出は、単なる中古車販売にとどまらず、現地の生活インフラや産業の一端を担う重要な役割を果たしています。
そのため、輸出事業者にとってもさまざまなビジネス的メリットが存在します。ここでは、6つの大きな利点について詳しく解説します。
高い利益率が期待できる
日本国内で10〜30万円程度で取引される中古軽トラが、海外では2〜4倍の価格で販売されるケースも珍しくありません。
特に北米やオセアニア市場では、「状態の良い日本製軽トラ」に対する信頼が厚く、現地のニッチな需要に刺さることで、高額取引につながります。
たとえば、走行距離5万km未満・4WD・MT・キャブ付きなどの条件を満たす車両は、米国で3,000〜5,000ドル(約45〜75万円)以上で取引されることもあります。
仕入れ価格に対して粗利率が大きく、ビジネスとして非常に魅力的です。
また、現地通貨が強い国(ドル高など)をターゲットにすることで、為替メリットも享受でき、売上アップに貢献します。
日本製車両への信頼と現地ニーズの高い適合性
軽トラは「小型・堅牢・経済的」という特徴を持っており、発展途上国から先進国まで幅広い地域で需要があります。
農作業、配送、建築資材の運搬、敷地内移動など、用途が多岐にわたるため、「とにかく使いやすく壊れにくい車両」が求められる現場で特に重宝されています。
たとえばアフリカでは、トヨタ・ハイラックスのような大型ピックアップが普及する一方で、維持コストが高く手の届きにくい層にとって、軽トラは実用的で手頃な選択肢となっています。
道路事情が悪くても耐久性があり、積載量も実用的で、特に現地の中小事業者にとって「最初の事業車両」として選ばれることが多いです。
燃費性能・維持費の安さによる優位性
軽トラは一般的に660ccの小型エンジンを搭載しており、燃費は平均で17〜20km/Lと非常に優秀です。
さらに、車両自体が軽量であるためタイヤやブレーキの消耗も少なく、日常的なメンテナンスも簡単です。
このような特徴は、燃料費の高い国や経済的に制約のある層にとって非常に重要です。「購入後も安心して使える」という維持コストの低さが、販売のしやすさや再販率の高さに直結します。
また、保険料や税金も安価で済むため、都市部の自営業者や農家、個人オーナーにとっては導入しやすい車両となります。
用途の多様性とカスタマイズ性の高さ
軽トラのシンプルな構造は、「改造ベース車両」としても非常に優れています。輸出先によっては以下のような活用が行われています:
キャンピングカーへの改造:米国やカナダでは軽トラをベースにした“ミニキャンパー”が人気。DIY志向のユーザーに好まれる。
移動販売車(キッチンカー)への転用:フィリピンやタイなど、屋台文化のある地域で導入例あり。
オフロード仕様へのカスタム:タイヤやサスペンションを強化し、未舗装路に対応する仕様として改造。
このように、単なる「農業用軽トラ」としてではなく、多目的ベース車両としての価値が広がっているため、販売ターゲット層の拡大が期待できます。
構造のシンプルさと修理のしやすさ
軽トラはエンジンや電子機器の構造がシンプルで、パーツの互換性も高い車種が多いため、現地での修理やメンテナンスが非常にしやすいのが特徴です。
高度な診断機器が必要ないため、町工場や個人整備士でも対応でき、ユーザーにとっては「壊れても安心して使える車」としての評価を得やすいです。
さらに、中古パーツも日本から継続的にの供給が可能で、長期的な使用を見越した購入がされやすいのもメリットです。
法制度の後押し(例:アメリカの25年ルール)
アメリカでは「25年ルール」により、製造から25年以上が経過した車両は、米国の連邦安全基準や排ガス規制の適用を受けずに輸入・登録が可能となります。
この制度により、1990年代のスズキ キャリイやダイハツ ハイゼット、スバル サンバーなどが続々と米国へ輸出されており、軽トラブームを支える一因となっています。
また、アメリカ以外でも、古い車両の輸入を容認する国(例:ニュージーランド、モンゴル、ケニアなど)では、このような制度を活かして輸出ビジネスを展開することができます。
軽トラック(軽トラ)の海外輸出時のリスクやデメリット

軽トラックの輸出は、高利益を狙える一方で、さまざまなリスクと常に隣り合わせです。
とくに中古車を海外へ輸出する場合、車両の状態や輸送・通関のトラブル、為替の急変、各国の法制度の変化など、ビジネスを脅かす要素は数多く存在します。
ここでは、軽トラ輸出における主なリスクを5つのカテゴリに分類し、具体的な内容とその対策の方向性について詳しく解説します。
各国の規制・コンプライアンスリスク
海外への輸出では、各国の輸入規制や税関手続きに対応する必要があり、その内容は国ごとに異なります。
輸出先を間違えると「輸入不可」や「高額な罰金」「車両の没収」といったリスクにつながるため、常に最新の法令や規定に注意が必要です。
主なリスクの例
■年式制限のある国
ナイジェリアやスリランカなどでは、一定年数以上経過した車両の輸入が制限されており、出荷後に通関できなかった事例もあります。
右ハンドル規制:南米諸国や中東の一部では、右ハンドル車の登録が制限または禁止されています。
排ガス規制の強化:タイやシンガポールなどでは、一定の環境基準(EURO規格など)をクリアしていない車両は輸入できません。
■対策
輸出前に輸入規制の一覧を整理しておく(年式・ハンドル位置・排ガス・車両サイズなど)
現地通関業者との情報連携を密に行い、JETROなどの公的機関や、現地大使館の貿易部門から最新の制度情報を取得する。
為替リスク・貿易摩擦リスク
輸出ビジネスにおいて為替の影響は避けて通れません。
円安で輸出が有利な時期もあれば、円高に振れると利益が縮小するリスクもあります。
また、輸出先の通商政策の変化によって、関税や取引条件が突然変更されることもあります。
■想定されるリスク
急激な円高での為替差損:ドル建てで取引している場合、為替が数円動くだけで実質的な売上が数万円単位で減少することがあります。
関税の引き上げや輸入制限措置:アメリカや中国などでは、自国の産業保護を目的に中古車輸入への関税強化が行われる可能性が常に存在します。
■対策
為替予約(フォワード契約)を活用し、リスクをヘッジ。
そして、複数の国・地域に輸出先を分散し、マーケットリスクの平準化を図り、主要国の通商ニュースをウォッチしておく(WTOやEPAの動向)。
物流・通関・輸送に関するトラブル
中古車の輸出では、海上輸送・通関・検疫といった物理的なプロセスも多く、その中でのトラブルも少なくありません。
特に近年ではコンテナ不足や港湾混雑、書類不備による積み残しといったリスクが頻発しています。
■想定されるリスク
コンテナ予約の確保が困難:世界的な物流混乱で、特定の航路では船便が1ヶ月以上先になることもあります。
通関書類のミスや不足:インボイスや輸出抹消証明書に記載ミスがあると、貨物が保留され、保管料など余計な費用が発生することがあります。
税関検査の遅延:特定の港では税関が混雑しており、検査だけで数日〜1週間待たされることもあります。
■対策
輸出に慣れた実績豊富なフォワーダーを起用する。また、書類はダブルチェック体制をとる。必要なら行政書士や通関士に依頼します。さらに、港湾の混雑状況を把握し、複数港を比較検討するのが良いでしょう。
取引・支払いトラブル
輸出取引の相手が海外の個人・業者である場合、代金の未払い、トラブルの長期化、詐欺の被害といったリスクも考慮すべきです。
とくに先払いを要求されないCIF契約などでは、回収不能リスクが顕在化しやすくなります。
■事例
- バイヤーが代金を支払わず失踪
- 現地到着後に「車両の状態が違う」と言われ、価格を下げさせられる
- 現地の業者とトラブルになり、車両が保留される
■対策
- 可能な限り信用状(L/C)やエスクロー決済を活用する
- 取引先の事前調査を行い、与信管理を徹底する
- 少額取引からスタートし、信用が確認できてから本格的な輸出へ移行する
車両の損傷・品質問題・保険リスク
輸送中の損傷や盗難、出荷時の車両の状態に起因するクレームは、後々の関係性にも大きく影響します。
特にフレームのサビや機関系の不調が現地で発覚すると、返品や返金を求められるケースもあります。
また、保険料も年々上昇しており、輸送リスクを無視した輸出は危険です。
■リスク例
- コンテナ内で車両が動き、ドアやフェンダーが破損
- 海上輸送中に盗難に遭い、車両が行方不明
- 現地でサビ・腐食が発覚し、価格交渉を強いられる
■対策
- 海上保険(輸送保険)は補償内容を確認して加入
- 車両は出荷前に第三者検査(JEVICなど)を通す
- 輸送方法(コンテナorRoRo)の適正判断を行い、安全性を優先する
まとめ
この記事では、軽トラが海外で人気を集める理由や主要な輸出先、現在の市場動向、そして輸出を始めるための手続きや必要な準備について詳しく解説しました。
仕入れ時のチェックポイントや、輸出のメリット、そして気をつけたいリスクについても実務的な観点から取り上げています。
日本の軽トラックは、そのコンパクトなサイズ・高い燃費性能・耐久性の高さなどから、世界中で高く評価されています。
特に北米、アジア、アフリカを中心に、農業用・商用・レジャー用途として多様なニーズが広がっており、中古軽トラの輸出は年々拡大傾向にあります。
軽トラ輸出は、うまく進めれば高い利益率を得られるビジネスである一方で、書類の不備や規制変更、為替・物流コストの変動など、綿密な情報管理とリスク対応が欠かせません。
成功のカギは、最新の市場情報を常に把握しながら、信頼できる取引先や業者と連携し、丁寧に準備を積み重ねていくことにあります。
今後も日本の軽トラは、実用性・コストパフォーマンス・改造自由度といった面で海外からの注目を集め続けるでしょう。
中古車市場に新たな商機を見出したい方にとって、軽トラ輸出は非常に魅力的な選択肢のひとつです。
まずは情報収集と市場リサーチから始め、信頼できる輸出パートナーを見つけることから一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。
最後に
当記事でピックアップした軽トラックを始め、海外では魅力的な中古車が日本に眠っており界隈ではビジネスチャンスとして中古車輸出が注目されております。
中古車輸出の魅力は、資源の有効利用と経済的なメリットにあります。
中古車両を再利用することで、環境への負担を減らしつつ、経済的な利益を得ることができます。
また、新興市場では日本の中古車が重要な移動手段として社会に貢献していると言えます。
AUTOHUBのような専門的なサポートを利用することで、中古車輸出は実現可能なビジネスになりえます。
実際、巨大な船会社や通関業者と直接取引を行うことは、一握りの大手や老舗中古車輸出業者以外では困難です。
多様な市場に対応し、適切な手続きとサポートを受けることで、日本の中古車輸出業者は新たなチャンスを掴むことができるでしょう。
中古車輸出を検討している方は、ぜひAUTOHUBのサービスをご利用ください。安心・安全な輸出プロセスで、ビジネスの成功をサポートいたします。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

